スーパーのオンライン化の先に見据えるものは?10xを実現するBizDev/Corp #10Xtopicレポート
10Xが日々取り組むプロダクトづくり、仕事内容をカジュアルにお話しするオンラインイベント「10X Topic」。
2020/9/14に開催した第3回では、「10X Topic #3 社員15人で業界最大手との提携を実現するBizDev&Corp」と題して、CEOの矢本真丈がBizDev全体の方針を、BizDevの赤木はBizDevの実際のフローについて、CFOの山田からは10Xの成長を支えるパートナーとの契約や管理会計・ファイナンスの考え方について、お話させていただきました。
本記事では、トークセッションでいただいた質問について、以下4テーマに分けてお伝えします。
-パートナーとの事業開発のポイントについて
-ネットスーパーの業界特性・難しさについて
-10Xの未来、数年後に向けたビジョン
-10Xのカルチャーについて
なお、各メンバーの発表については記事では触れていませんが、下記スライドとYouTubeにて公開していますのでぜひご覧ください。

矢本の発表スライドより抜粋
最大手からマーケットに入ることが“10x”を生む
-本イベントで一番多かった質問は「大企業とのアライアンスを実現する方法」について。交渉相手の選定や、各交渉相手へのヒアリング・提案方法、リード獲得方法など、具体的な質問が寄せられました。
赤木「10Xが他の会社と違うと感じる点は、商談プロセスにおいて自社サービスをプッシュせず、相手からニーズを引き出し相談したくなるステージに持っていくやり方だと思います。Stailerの営業トークをするのではなく、敢えて黙って相手の課題感を聞く。そして、我々が理想とする姿や実現したい世界感をブレずに伝え続ける。最初は期待値が合わない相手でも、こちらがブレなければ先方のフェーズが変わったタイミングで期待値が擦り合うことがあるんです。例えば先方の組織が変わったり、新型コロナウイルスの影響だとか。色々な変化によって、“10Xが言ったことってこういうことだったんだ”と思っていただけると、その後が早かったりします。」
-そもそも、大企業のリードはどう獲得しているのでしょうか。
赤木「『イトーヨーカドー』=『セブン&アイ・ホールディングス』という最大手との取引が始まったことのインパクトは非常に大きかったです。それにより多くのインバウンドのお問い合わせをいただきました。なので、実績を見せられると、その後のリード獲得に繋がると思います。」
※イトーヨーカドーとパートナーシップを組んだ経緯については「タベリーからStailerへ」もあわせてご覧ください。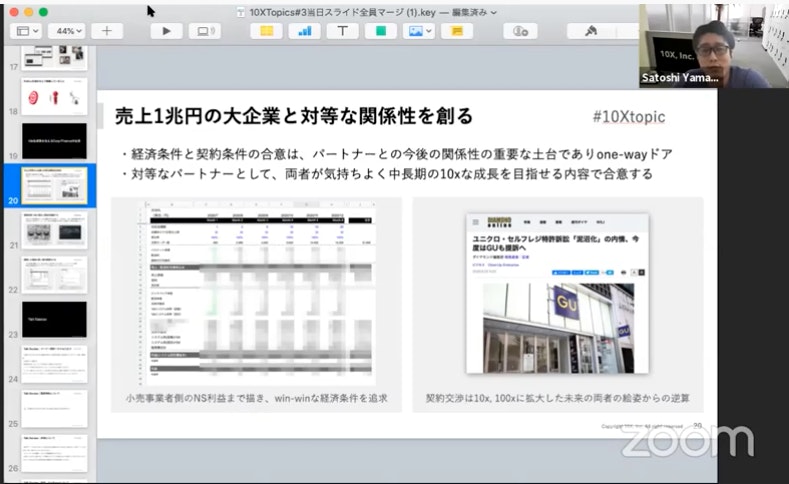
イベント本編ではCFO山田からパートナーとの経済条件の考え方についても説明
-提携企業数が膨らむと同時に自社の組織も拡大が必要そうですが、そもそも提供企業数は絞り込む方針なのでしょうか?
矢本「絞り込む方針ではないですね。むしろ、少ない人数でもスケールできるような形を目指しています。1人当たりの時価総額が高い会社を作りたい、1人当たりの生産性や創造性が“10x”な会社を作りたいんです。なので、本イベントのテーマでもありますが、20人で超大きなエンタープライズとパートナーシップを組むというのは10Xにとっては高いレバレッジがかかり、理にかなっていると思います。」
「発想転換できたら勝ち」ネットスーパー業界特有の楽しさ・難しさ
次は、ネットスーパーの業界特性・難しさについての質問にお答えします。
-食品小売業界ならではの苦労や、面白さや魅力などがあれば教えてください。
山田「月並みですが、自分の家族や親が我々のサービスを使ってくれて、自然にフィードバックをもらえるのはいいですよね。私の十数年のキャリアの中でも初めてです。我々はエンドユーザーの体験を起点に全ての物事を考えるスタンスなので、自分や周囲の人がエンドユーザーになれる業界の方がフィードバックループがかかりやすく相性がいいと感じますね。」
赤木「これまで店舗を起点にずっと成長されてきた小売事業者さんにとって、店舗にお客さんをどう呼び込むか、店舗をどう作るかは手に取るようにわかっても、オンラインは想像がつかない世界なんですよね。なので、全然違う商売であることに気付いて発想の転換ができれば、他の会社と差別化ができる。ポテンシャルあるなと思う会社さんもいくつかありますが、最初の一歩を踏み出す部分や、社内の体制整備が大変そうだなと思う会社さんもあります。」
-日用品ECならではの難しさはありますか?
矢本「単価(粗利)が低い、ということに尽きると思います。例を上げると、僕が始めて参加したスマービーという子供服ECのスタートアップで扱っていた商材は高くて2、3,000円。これもアパレルの中では単価の低い商材でした。例えば自動車と子供服の粗利率が同じ3割だったとしても、単価は片や300万円で片や3,000円。一回のトランザクションで得られる粗利に大きな差があります。他方でそれぞれ1つ販売するのに必要なシステムや運用に1,000倍の差があるかというとそうではない。取引あたりのシステム効率、オペレーション効率みたいなもので比較すると大きな差があるかもしれません。
僕は生活に密着した購入頻度が高い商材に惹かれます。頻度が高いものとはすなわち、無くてはならないものだと思うんです。ペイン4象限で表現すると、食品は頻度が高く、イシューとして重い。個人的には一番難しい領域だなと理解しつつ、チャレンジしているという感じですね(笑)。」
スーパーのオンライン化の先にはデータ活用・FinTechも視野に
次の質問は、10Xの未来について。
-国内マーケットだけでも巨大ですが、国外マーケットに進出することは考えていますか?
矢本「スーパーや小売事業って、明確な国境ボーダーがあるんですよ。インターネット社会なのに、めちゃくちゃローカルな事業で、ローカルの品揃えに対してローカルのエンドユーザーがつく事業モデルです。例えば『インスタカート』(Instacart)もアメリカから出ていないですし、『フーマー』(盒馬鮮生)※だって中国から出られていない。なので、国外は現在は考えていないです。国内だけでもかなり大きな市場であり、国内のイシューだけでも物凄く大きいので、それをしっかり掘ることが重要だと思っています。
あわせて、Stailerの次の展開もお話すると、様々な小売事業をオンラインに乗せることが第一段階で、第二段階は、そこに集まってくる貴重なデータを活用することだと思っています。食品メーカーさんは、マスにリーチするために小売に依存せざるを得ないんです。『味の素』をまとめて5キロ買えるとしても買う人はおらず、生鮮や日配品など他のものと合わせて買ってもらう必要があるので、ワンストップショッピングに価値がある。これはオンラインになっても変わりません。
現状だと、食品メーカーさんは小売店舗に営業に行って販促費を払い、特販の棚を取っています。ただ、その特販の結果、いくら使っていくらの売上が増えたのかという具体的なROIは全然見えていない。そういうものをオンラインの販売チャネルを通して、ガラッと変えるチャンスはあると思っています。要は、プラットフォーム上で商売をされている方々向けのソリューションが作れるんじゃないかと考えています。」
※Instacart:アメリカの食料品・日用品買い物代行・即日配達サービス
※盒馬鮮生:アリババが中国で運営する店頭販売、宅配EC、レストランなどを融合させた核心的スーパー
山田「私も前職でビールメーカーやお菓子メーカーへの投資をしていたのですが、商品開発部は大手スーパーのバイヤー向けに商品を考えているんですよね。棚の面積をどれだけ取れるかで売上が決まってしまうのですが、バイヤーに気に入ってもらえば棚に並ぶし、そうじゃないと売上が落ちる。ここには非合理があると考えており、10X入社前から矢本ともディスカッションしてこの分野の可能性に共感していた点でもあります。」
-ネットスーパーの次は、どのような事業展開を考えていますか?
矢本「GMSを中心とした流通小売は、1階の食品売場でお客さんを獲得して、2階でアパレル、不動産、保険を販売する事で利益を稼いできた歴史があります。その最終形が金融です。例えば、『セブン銀行』は特殊な事業で、預かり資産の運用益ではなく、単純な取引手数料だけ多くを稼ぐ金融事業です。高頻度でお客さんが来る場所、商流の一番の入り口を押さえているから『セブン銀行』が生まれたという背景は有名です。
これをデジタルに置き換えて、我々も同じようなチャレンジが将来的に狙えるのではないかと考えています。
『イトーヨーカドー』のアプリのユーザーの利用頻度は非常に高く将来的にリテール向けのフィンテックでも新しいイノベーションを作れるのではないかと思っていて。長い目で見てワクワクしている部分ですね。」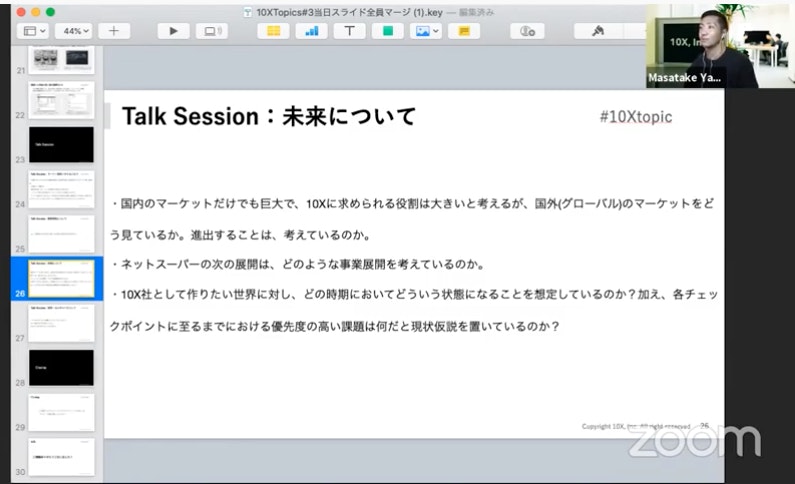
-10Xが作りたい世界に対して、どのような時期にどのような状態にあることを想定していますか?
山田「『イトーヨーカドー』という大手をしっかりサクセスさせて、彼らのネットスーパーのGMV(流通総額)がユーザー体験の向上を通して劇的に伸びていくことを立証するのが一つ。もう一つは、地方のスーパーの(オンライン化の)ゼロイチ立ち上げをしっかりやっていくこと。まずは、この二つをやるべきで、達成した後にN数を増やしていくことになると思います。
スピード感については、小売は、パートナーの事業立ち上げのスピード感やエンドユーザーの行動変容のスピード感もあるので、1年先か1年半先かは今はわかりません。だからこそ我々は、この市場に長期でベットし続けられるように、資金調達や組織開発のあり方も考えています。」
キーワードは「逆算」「自律」「透明性」。10Xに向く人、向かない人
最後は、10Xのカルチャーについての質問です。
-10Xのメンバーは、どのような方が多いのでしょうか
赤木「10Xでは年齢関係なく、非常に落ち着いた大人な人が多いイメージです。社内で活躍している方に共通していることは、10Xという名前の通り、10倍の価値から逆算して動ける、自律性が高い人ですね。前職の大企業では一つ一つプロセスを踏み確認をする進め方をしてきたし、当たり前だと思っていたのですが、10Xでは、気づいたらもうできている。誰かに任せるとか、確認をするとかではなくて、自身がドライブしていく人が全員じゃないかな。逆に、そういう人じゃないと活躍するのは難しいかもしれません。」
山田「“この仕事(タスク)をよろしく”と頼まれるわけではなく、もっと大きなイシュー単位で、自分の枠にとらわれず、どんどん自律的にやっていく方が圧倒的に多い。変に線引きをせずに、チャレンジングなこと・新しいことに取り組むのが好きな人が多いですね。
入社して半年程度ですが、経営会議の議事録や人事評価までオープンなど、情報共有の仕組みのトランスペアレンシー(透明性)が非常に高いことにも惹かれています。」
10Xでは、ミッション・バリューから年収や評価基準、SOインセンティブ制度まで、さまざまな情報を社外に向けても公開しています。また最近では、社員全員が会社のカルチャーやCEOを評価する「CEOレビュー」を実施し、その結果を赤裸々に公開中。「透明性(オープンさ)を高く保つこと」は、10X行動指針の一つでもあります。10Xの公開情報はこちらにまとめていますので、ぜひご覧ください。
-正社員か、業務委託か、現段階で業務形態にこだわりはありますか?
矢本「会社のコアとなる業務については、基本的にはフルタイムの正社員を募集しています。これは、イシューに対して深堀りして”10xから逆算する”を実現してもらうには、深入りしないと出せない価値があると考えているからです。ただ、採用の過程において、候補者の方と我々お互いのカルチャーやスキルがフィットするのか見るためには、一緒に働いてみるのがベストだと考えているので、採用プロセスでは”トライアル”として最低1日は実際に働いていただくプロセスを設けています。また、正社員としてのジョインを見据えた過程で、お互いのことを知るという目的での副業という働き方は活用していきたいと考えています。」
以上、オンラインイベント「10X Topic #3 社員15人で業界最大手との提携を実現するBizDev&Corp」の模様をお届けしました。
全編動画も公開しています
本イベントの内容は、YouTubeにてアーカイブを公開しています。
この記事に関連する求人情報
10Xでは一緒に「社会に10xを実装する」仲間を募集しています!
興味をもって頂いた方は、ぜひ下記の募集要項と「Culture Deck」をご覧ください。
ビジネスディベロップメント



