スケールに耐えうる“契約・請求管理”のあり方を徹底議論!
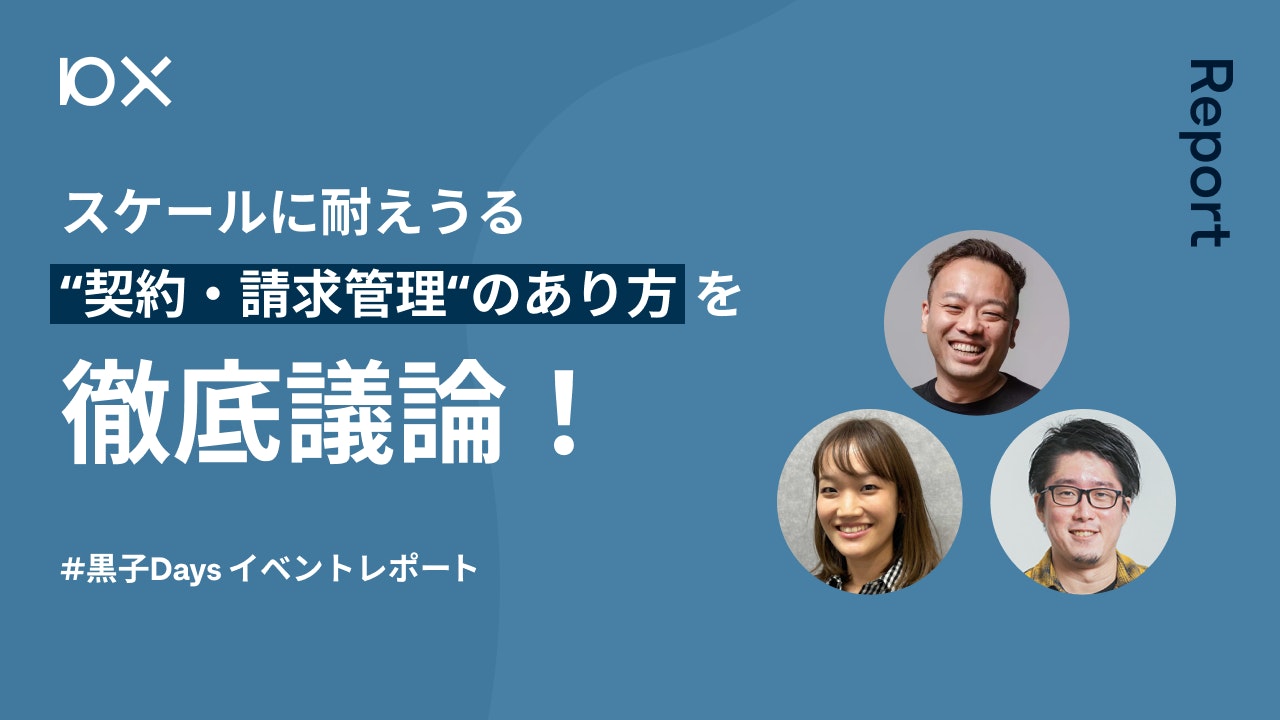
契約・請求管理にある“攻め”の要素を、いかに事業価値向上へつなげていくか?
「売れてなんぼ」なBtoB事業をスケールさせていくために、コーポレートはどのような考えを持っておくとよいのか?
「急成長スタートアップの裏側を支えるコーポレート部門大集合」ということで開催されたオンラインイベント「黒子のコーポレート大激論 Days」。今回は人気セッションとなった「急成長企業の契約・請求管理と事業価値向上への貢献」のレポートをお届けします。登壇したのは、アルプ執行役員CROの毛利悠記氏、10X Corporate Operations部マネージャーの川村優季氏、モデレーターは10X取締役CFOの山田 聡氏。“お金の管理”を司る契約・請求管理だからこそ、スケールに備えて今からやっておいたほうがいいこととは?
2009年に株式会社ワークスアプリケーションズに入社。HR・AC領域を中心に日系大手企業向けのERPセールスに約10年従事し、営業責任者として事業を牽引。2019年にアルプに出会い、1人目セールスとして入社し、セールスとカスタマーサクセスを中心にレベニューオペレーション全般を担当。2022年7月にCROに就任。
決済代行企業にて上場準備PJや新卒採用などに従事。その後、2016年よりコネヒト株式会社にてバックオフィス部門の立ち上げ・業務統括、社内組織開発PJ等に携わる。2022年1月より10Xに入社。好きなものは朝ドラ。
三菱商事株式会社でロシア・カザフスタン向けの自動車販売事業・現地販売会社のM&A及びPMIを経験。その後、米系PEファンドであるCarlyle Groupに参画し、おやつカンパニーやオリオンビールの投資・PMIを実行。Wharton MBA(2017年)。10X以外にもVoreas北海道を始めとするスポーツチームの経営支援に関わる。
契約・請求管理のスケールで課題になる「不確実性」「複雑性」
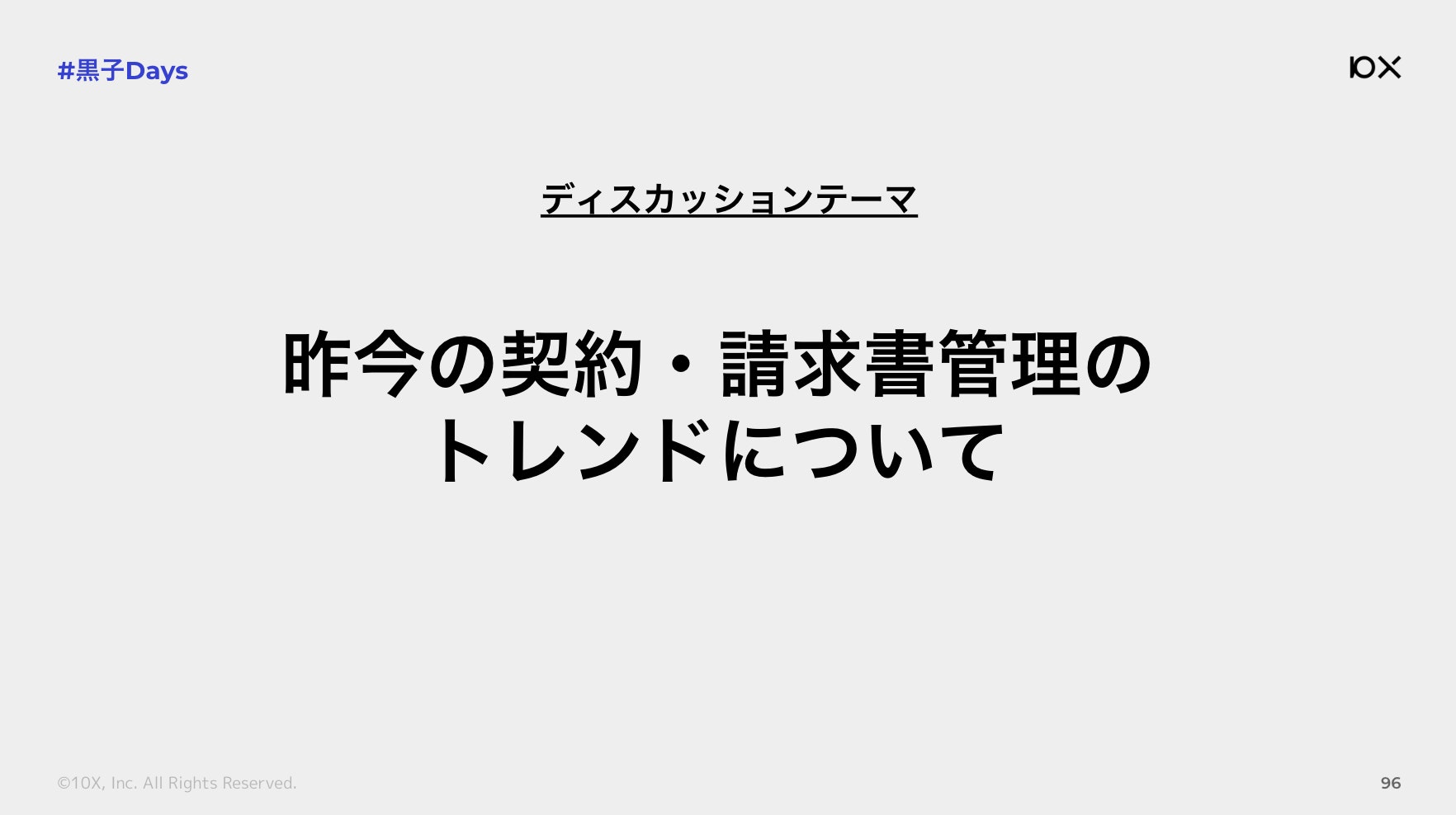
山田:本セッションでは「契約・請求管理やオペレーション」という渋いテーマを設定しました。当然ながら売上は大事ですし、急成長するスタートアップでは取引先もどんどん増えていきます。さまざまなプライシングを用意したり、スケールに耐えられるオペレーションにしておくことは成長維持のためにも重要です。そんな課題意識から生まれたテーマでもあります。更に、契約・請求書管理は実は守りだけでなく「攻め」の要素もあり、売上や事業成長にどう貢献していくのか…という話をできればと。まずは川村さんから!
川村:10Xでの契約・請求管理の現状と課題からお話ししますね。前提として、10Xが取引するパートナーは一社一社がとても大きいけれど、全体の取引社数はまだそれほど多くないんです。そのため、がっつりとした管理システムがなくても、手作業でなんとかなってしまう。具体的には、新規契約が成立したら、その状況をスプレッドシートに入力。毎月月末になると担当者が請求額をスプレッドシード上で計算し、それを請求書発行システムに反映する流れです。
ただ10Xは今、会社をよりスケールさせようとしているので、それに伴い契約・請求管理での手作業もやめなければと思っているんです。そこで課題に感じているのが「料金体系の不確実性」「契約条件の複雑性」の2つ。
まず「料金体系の不確実性」について。10Xのビジネスモデルには基本的な料金体系があるものの、パートナーによってプライシングを調整することもあります。なかには「今月はちょっとイレギュラーだけど、この請求ものせてほしい」という要望も。そのため、一元的にデータを整え、完全自動化するのはなかなか難しいと感じています。備考欄に特記事項として書いてもらう手段があるかもしれませんけれど…結果的にシステム上で計算できなくなる可能性が高い。取引量が増えるとより深刻化するので、なんとかしたいです。
「契約条件の複雑性」では、契約条件を変えるところはBizDevや法務がメインだけれど、最終的な請求は経理が担当する難しさを意味しています。このやり方を維持しようとすると、BizDevや法務の動きを常に把握し、正しい情報を請求管理システムに反映し続ける必要がある。さらに、契約条件が請求に反映され始めるタイミングも条件によってバラバラなので、その情報も正しく管理する必要もあり…今後スケールしていくことを考えると、間違いなく大きな課題になります。
山田:CFOとしてプライシングを調整する機会がありますが、いつも川村さんたちにたくさん苦労をかけているのだ…と思いながら今の話を聞いていました(笑)
川村:いや、むしろそういった業務も今後より強化していく自信はあるので、現場のメンバーには「好きにやってこい!」と言いたいんです。とはいえ、実はヒヤヒヤしていますけれど(笑)。
「toBは商品は売れてなんぼ」を支えるコーポレートの存在
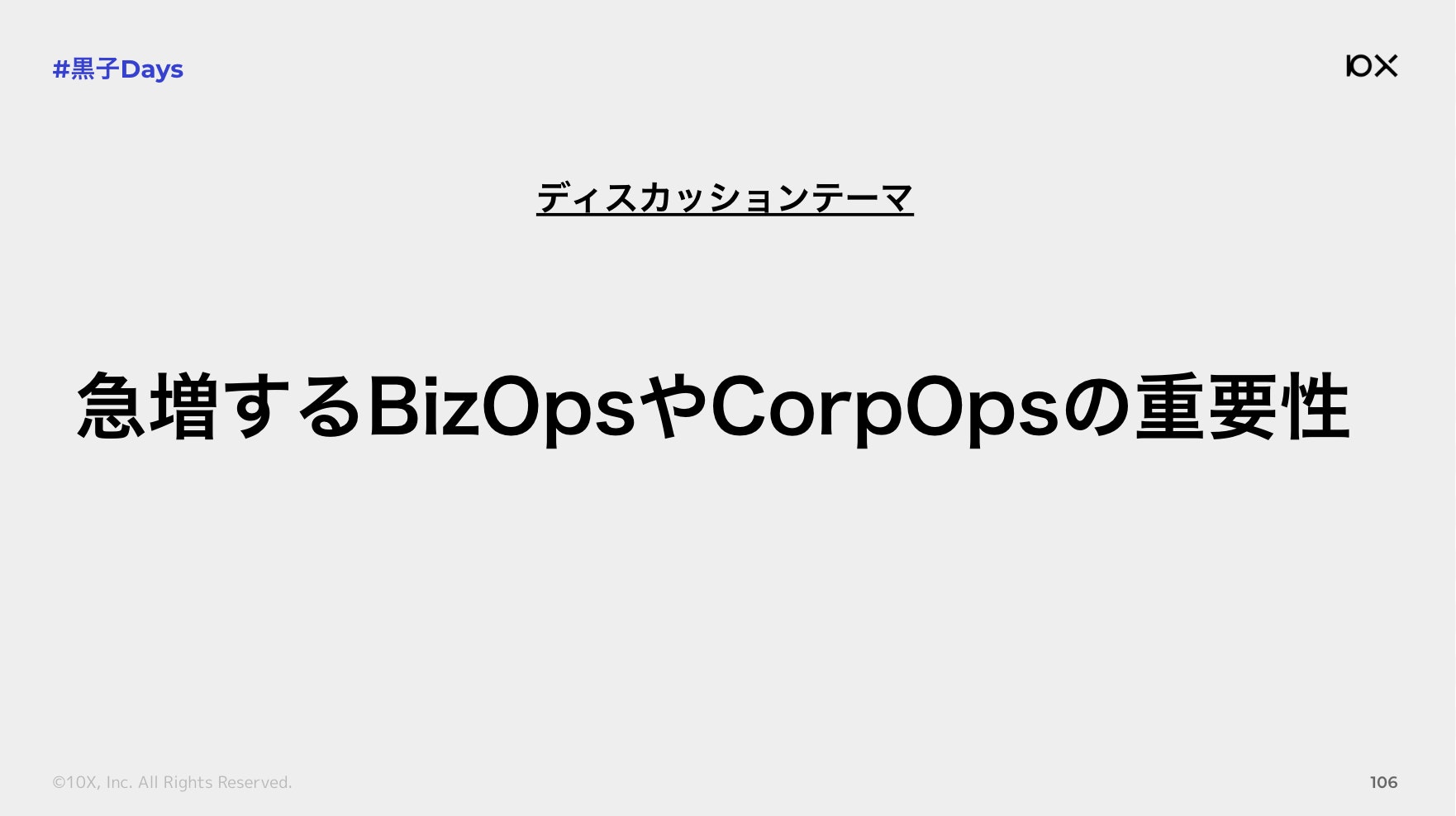
山田:毛利さんはどうですか?
毛利:アルプでも10Xさんと同じく「特殊な契約条件すぎでしょ!」と言われそうなものがあり、経理担当者たちに負荷をかけています。多くの会社がそうだと思いますが、事業では「売れる」ことが正義なので、そのために特殊な条件を受け入れるというのはあるある課題です。
商品の売り方には「セルフサーブでお客様が購入できるもの」と「営業が介在して購入するもの」の大きく2つがあり、管理の流れは概ね同じです。そこにどれくらいのイレギュラーが発生するのかによって、管理手法も変わります。例えばBtoCで営業が介在しないモデルであれば、ホームページから申し込みが入り、クレジットカード決済されるまでを自動化できるのが理想です。
一方でBtoBでは多くの場合、営業が介在しています。そのため、お客さまごとのディスカウントや特殊な条件や、プランの組み合わせなどの工夫ができてしまう。さらに、BtoBはクレジットカードや口座振替のような決済方法は、小口の取引を中心に利用されていて、日本の法人間取引では、請求書払いが多いんです。それらをシステム設計時に考慮しなければならないわけです。
山田:視聴者の方から「個社ごとにイレギュラーな請求要望を所与として進めたいのか、もしくはそれ自体を自動化したいのか。どちらですか?」という質問も来ています。川村さん、どうですか?
川村:両方ですね。頻発するイレギュラーは、ちゃんとシステムに組み込んでおきたいです。現場メンバーに「システムに組み込めないからやらないでください」とは絶対に言いたくないので(笑)。BizDevのメンバーは、お客さまにとって一番ベネフィットがある料金体系の最適解を考えて提案しています。もちろん既存ルールやシステムに合わせることがところは合わせてもらいつつ、そうじゃない場合でも柔軟に受け入れられる体制を作るのが、私たちコーポレートの使命だと思っています。
山田:毛利さんは?
毛利:フェーズによるところは大きいと思っています。僕らの取引先だと成熟した事業状況のお客様では、内部統制のような考え方があり、定められたルールどおりに売ることが重要になる傾向が強いです。
一方で、今の僕らのフェーズのようなスタートアップは新しいプロダクトや新機能がどんどん出て、プライシングも可変になっていくので、常にチューニングが必要です。それを受け入れる余力がコーポレートにあるかどうかは事業存続において大事なポイントです。何より、とてもありがたい存在ですよね。
山田:川村さん、いつもありがとうございます!
川村:がんばります!
毛利:(笑)。
山田:毛利さんのおっしゃるとおりですね。10X代表の矢本と僕でよく議論するのが「プライシング自体がプロダクトである」ということ。プロダクトと同じく「いい価格帯を狙う=PMFを探る」となります。PMFすれば「このお客さまはこのプライシングがはまる」とわかってくる。その感覚をつかむためにも、振り返ってみると、初期フェーズは、プライシングに対する柔軟さを持てたこと自体が強みになっていたのだと毛利さんの話を聞いて思い出しました。
契約・請求管理の属人化から脱する3つのヒント
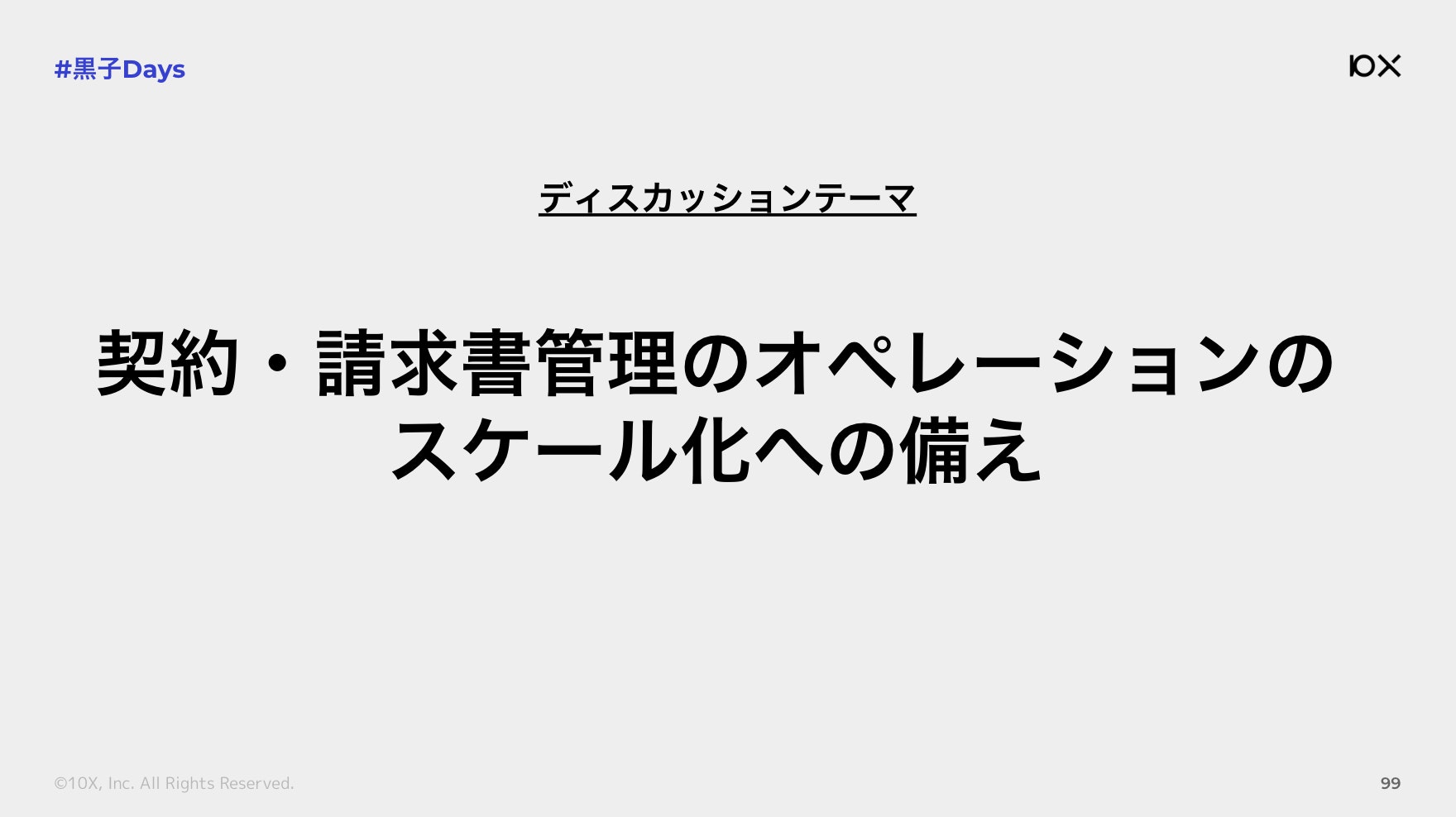
山田:次のテーマは「今後のスケールにどう備えるか」。まずは川村さんから。
川村:これからの10Xは、取引社数も組織もどんどん拡大していきます。
契約・請求管理の観点では、取引社数や契約条件のパターンが増えると、スプレッドシートでの運用に物理的な限界が見え始めます。つまり、多くの情報を正しくインプットし、複雑な関数を組んで請求金額を正しくアウトプットすることはとても難しい。この課題を解決するには、ゼロベースで契約から請求書管理までのオペレーションを再構築し、取引社数が増えても動じない体制が必要。かつ、正確性を担保できる状態を作らなければならないと思っています。
もう1つは、組織内に蓄積される情報をどうするか。契約や請求関連の情報への社内ニーズは高まっていきます。関わる人が増えると、やはりそれぞれのニーズに応じた情報をスプレッドシートで管理することの煩雑さは増しますし、悪意なく情報を書き換えられてしまうリスクも高まります。
とはいえ、わかる人にしかわからない状態で情報がまとめられていても意味がありません。なので、いつ誰が見ても最新の契約条件や請求の履歴がわかる状態にしなければならない。例えば、それらの情報を基にしてプライシングの次のモデル構築や事業戦略に活かしてもらうなど、よりシームレスなオペレーションに変えていきたいと考えています。
山田:属人性を排除していくフェーズですよね。毛利さんはいろいろな企業を見てきたかと思うのですが、だからこそ「これをやっておくといい」みたいなものはありますか?
毛利:3つあります。1つ目は「あらかじめ理想形を描いておくこと」。会社内の誰が使っていて、どれくらいの請求をして、どれくらい売上を計上しているのかは大切な情報です。しかし、みんなが関係しているから、各所でスプレッドシートを触ることになります。そのうえ、従量課金制ならトランザクションを入れて計算しなければならないし、社長や経営陣に見せるためにサマライズした数字をどう見せるかを考えなくちゃいけないし…。情報の出どころがバラバラなだけに管理も運用も統一するのが難しい。最初から「こうやりたい」を考えておくのは大事なポイントです。
2つ目は「中長期の目標を定める」です。先ほどお話ししたように、サービスの価値が広がるにつれて価格を上げたり従量課金を始めたり、または新サービスを始めることもあります。その時々の断面の情報で判断するのではなく過去の契約の変遷をもとにした、正しい情報がなければ判断しづらいです。中長期的な視野でオペレーションを構築することをおすすめします。
そして3つ目は「特殊性をシステムや仕組みで内包する余地を作る」。最近では料金モデルの複雑性が高く、スプレッドシートで運用していても「四次元なの!?」と思うような計算式が組まれ請求書にするケースなどもあります。そのほか、お客さまごとの割引や支払い条件に合わせるケースも多いです。10Xさんのようにエンタープライズのお客さまを多く抱えていると、支払いサイト上での支払期限が60日と決まっていて、交渉の余地がないこともあります。
ビジネスサイドからすると、ビジネスを存続させるために個々のお客さま対応は重要です。ところどころで起こる特殊性を受け入れられる余地は、作っておいたほうがいいですね。
「システム化したい」と思ったらまずやりたいこと
山田:ある程度事業や収益モデルの形など将来の状況を予測をしないと仕組み化が難しいと思っています。毛利さんから見て、スタートアップ企業は、こうした将来の絵姿について解像度を持って進められるケースが多いのか、それとも相談するなかで「こういうものもあった」となるケースが多いのか、どちらでしょうか?
毛利:我々のお客さまには、「最初から従量課金をしていてすでに大変な人」もいれば、「近い将来に従量課金をやるから早めに入れておきたい人」もどちらもいます。
そのなかで感じているのは「困ってからのオペレーション再構築は大変」という事実です。先ほどご紹介した2つ目のポイント「中長期の目標を定める」でもお話ししたとおり、5〜10年経ったころに「過去のデータを見返そう」としようとしても、事業が多くなればなるほどその労力も時間もかかります。エンタープライズの会社は基幹システムを入れ替えるときに何百億円も何年もかかる場合もある。
なので「そろそろ悩むかも?」と思った瞬間に一度立ち止まっていただき、「我々の未来像はどうするのか?」を検討してみてほしいです。アルプでもプロダクトを販売するとき、お客さまに「投資対効果に見合っているのか」を考えてもらいます。なぜなら、将来の可能性に対してお金を支払っていただくかたちになるからです。そのうえで「お金がかかるかもしれないけれど、コストよりメリットがあるから今のうちに整備しておこう」と判断してもらうようにしています。
山田:川村さんは「いつごろ仕組み化しよう」「こうやって整備していこう」と考えていたりしますか?
川村:今までの10Xは経理担当メンバーが2人だったこともあり、情報連携を密にして管理・運用できていました。まぁ属人的だったわけなんですけれども。それが今ちょうど取引社数も増えて「経理担当者を複数おいて冗長化を図るようになってきた」「営業担当側も増えてきて、人によってちょっとずつ契約を取ってくるプライシングモデルが違うぞ」となり始めている。どんなに組まれたスプレッドシートがあっても、何が正しい情報か誰もわからなくなるような危機感が高まりつつありますね。
「価値に見合っているのか」「それに沿った設計になっているのか」
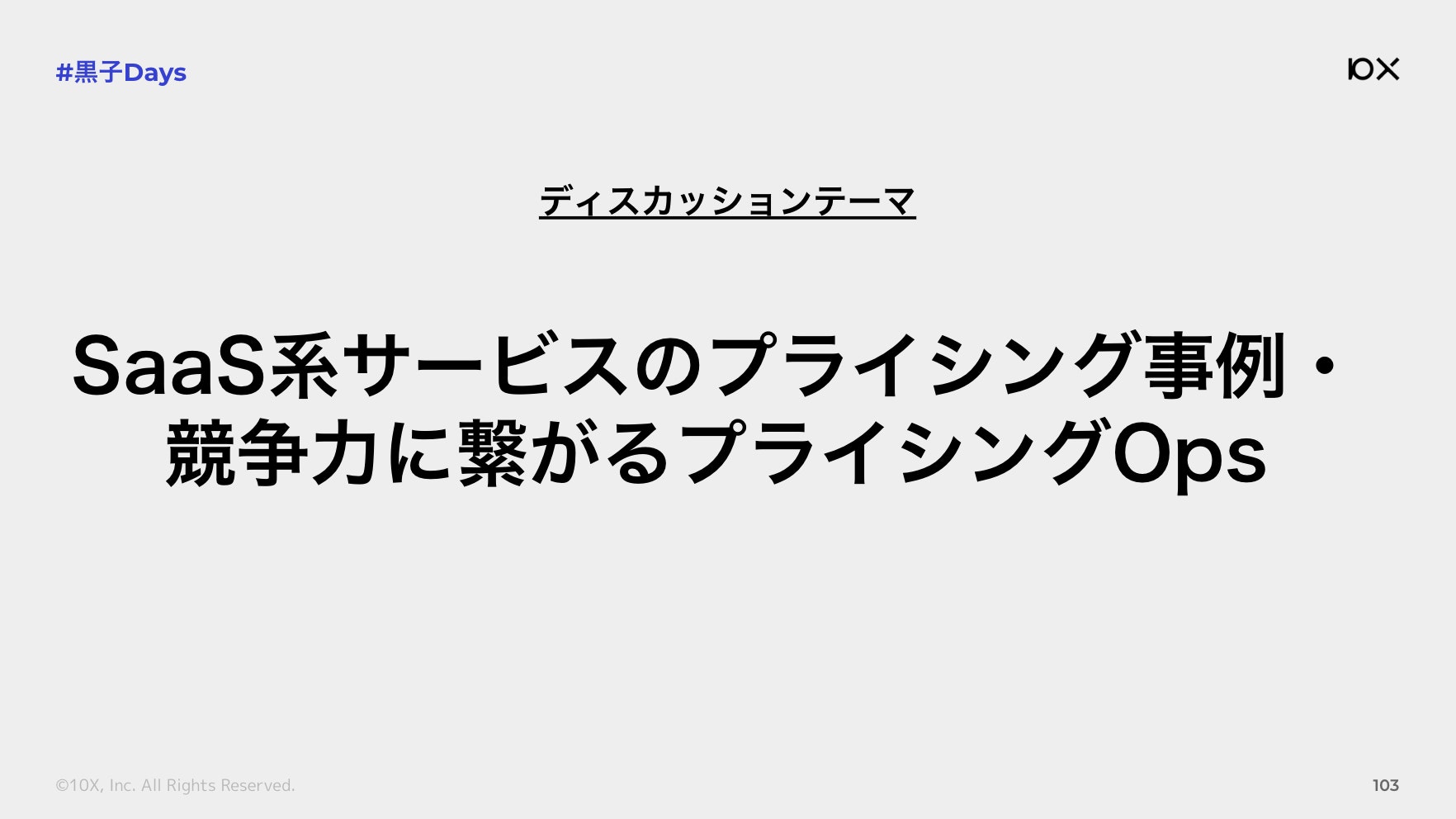
山田:最近、とあるSaaSのサービス営業を受けていて価格交渉をしていたんです。そうすると「その価格はシステム上入れられないんです」と言われてしまいまして…。プライシングを柔軟にできないところもあるんだと思ったんですよね。
プライシングを考えるうえで、いろいろなデータを分析することもあると思います。そのあたりの事例も聞いてみたいです。川村さんの場合、プライシングに対してフィードバックをしたところや、見えている世界観があれば教えてほしいです。
川村:そこまで見通せるほどの契約・請求書管理ができていない課題感はありますが…。本来はフィードバックできるくらいのデータを整備して、なんなら分析したものをお渡しできるのがベストです。でも、今は取引社数が増え続けていて、とにかく毎月正しく管理と計算をしてて間違いがないようにチェックして…という定常業務のオペレーションを回し続けることで精一杯です。ここは、どのようにオペレーションを構築すれば、事業に対するフィードバックもできるようになるのかを毛利さんに聞いてみたいところです。
毛利:僕らもプロダクトの提供だけでなく、プライシングのコンサルティングや設計もお手伝いさせてもらうことがあります。
前提として、プライシングに正解はないです。「値決めは経営」と言われるように、値段を決める方法にもいくつかあります。最近では「バリューベース・プライシング」という、お客さまが得た価値に基づいて価格を決める方法が主流だったりします。。SaaSだとどんどんアップデートし続けるので、最終的には対価が高くなって然るべきという考え方ですね。
一般的に多いのは、定額プランから始まり、従量課金と併用していくというパターン。価値を感じた分だけ対価をお支払いいただくモデルに切り替える会社は増えているように思います。そのなかで、自社プロダクトのバリューメトリクスがどこにあるのか、プライシングモデルがフィットしているのかを考えられる必要があります。それができれば、お客さまも我々も納得ができる課金ロジックを作れるんですよね。上場している企業でも、数年に1回は見直しをしたり価格を上げたり、プランを増やしたりなくしたりチューニングしています。
プライシングのポイントは、常に立ち止まり「価値に見合っているのか」「それに沿った設計になっているのか」を検討し、どういったお客さまにフォーカスするのかを考えることです。その際、欠かさないでほしいのが「(お客さまフォーカスの方向性を)オペレーションと戦略とあわせて考えること」。仕組みだけでなく、それに耐えうる構造であることも重要です。
プライシングもそうですが、事業拡大期はいろいろな新しい取り組みがあり、プロダクトもプライシングもチューニングしていくことになる。それを支えるのがコーポレートの醍醐味であり、難しいところです。
海外から見て「日本の環境はイレギュラー」である理由
山田:最後にQ&Aです。「ローカルな商習慣とSaaSがカバーしている機能とでミスマッチがあるのはイメージできるのですが、このあたりは日本独自なものであるイメージがあります。海外ではこのあたりどう対応して成長しているのか情報があればありがたいです」という質問がきています。これは毛利さんから話してもらったほうがいいですかね?
毛利:おっしゃるとおり、日本の環境はイレギュラーです。税制も税率も海外とは異なりますし、請求書もいわゆる掛け払いの概念です。日本の場合、業務システムを導入するときは基本的にカスタマイズする会社が多いです。業務システムに合わせるのではなく、自社のやり方に合わせるやり方をするわけです。また、日本は終身雇用型に考え方が近いのでご担当者が使いたいシステムを入れるようにする風潮もありますね。逆に海外の場合は「既存のシステムを使えない人は採用しない」という考えになる。そういった市場の違いもあります。
山田:我々も「Stailer(ステイラー)」を通じて、パートナーの方々にオペレーションシステムも提供しています。そこでは、毛利さんが話していることと同じ状況がありますね。現状のオペレーションを変えずにシステム的にサポートできるかどうか、そのためには現場のオペレーションをしっかり理解できていないとシステムの融合を進められない。日本の場合、海外以上に現場の存在は重要なんだと感じます。
そろそろ時間なので最後に、今日のイベントを見ている方々へのコメントや採用の宣伝などあれば!
川村:私はCorporate Operationsとして、コーポレート全体、さらにビジネス側へ染み出しながら横串でいい事業をつくる環境を整えようとしています。本日のイベントを通じて、コーポレートのニーズに合わせることだけではなく、10Xの事業環境や組織に合わせたシステムやプロセスを導入し、契約や請求管理をアップデートしていきたいと思いました。他社のOpsの方と議論する機会はそんなにないので「話しましょう」という方がいたら、声をかけてもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました!
毛利:僕の肌感でも、Corporate Operationsという部門は増えています。時代の流れとしても、ビジネスモデルの変化スピードがどんどん早くなっていて、それに対して柔軟に対応していく姿勢が求められています。同時に、事業を伸ばす観点でも重要なポジションです。我々も事業拡大を裏側から支えるプロダクトを作っているので、コーポレートで悩んでいる方がいらっしゃったらいろいろご紹介できればと思います。そして、日本をバックオフィスから支えられればなと考えています。今日はご清聴ありがとうございました。
山田:ありがとうございます。このトレンドがもっと盛り上がり、急成長するスタートアップがそれとともに増えるとうれしいなと思いました。お2人とも、今日はありがとうございました!



