CEO矢本とデータサイエンティスト谷口が語る、データ基盤で実現できる小売企業のDXとは
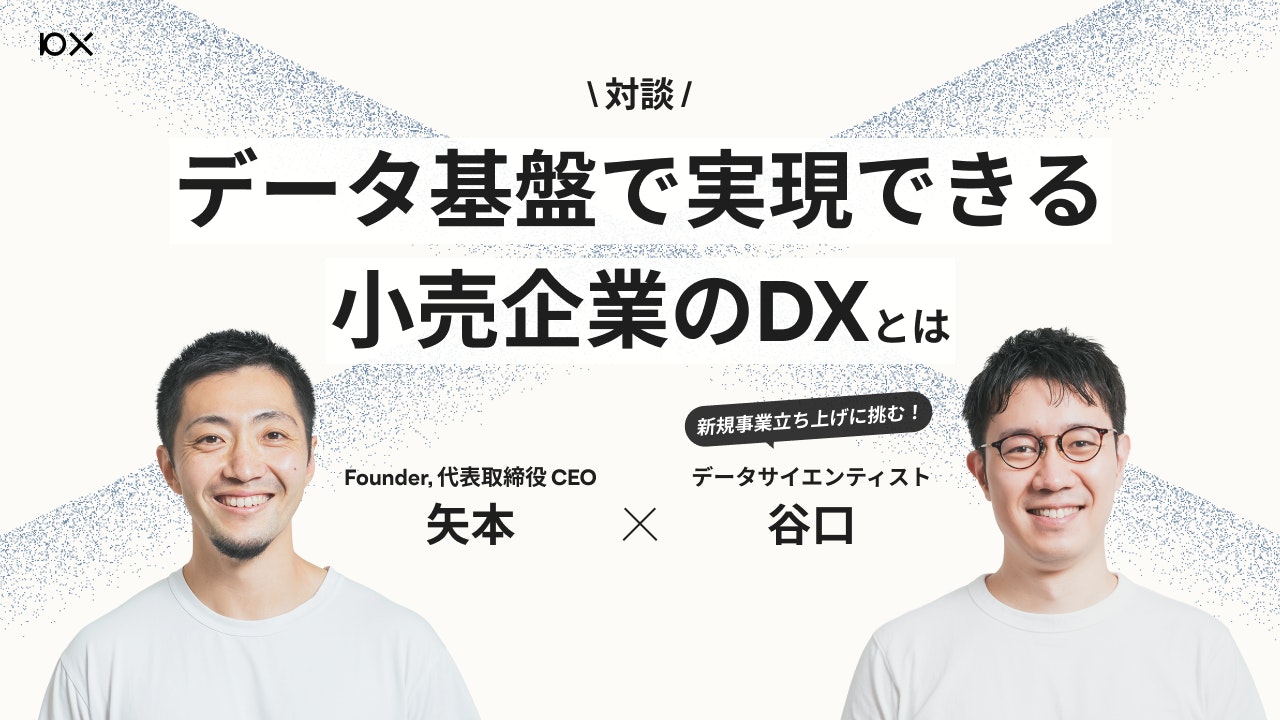
「Stailer」を通じて、日本全国のパートナー企業とタッグを組み、ネットスーパーの立ち上げを支援してきた10X。2025年5月に、小売業界を支援する5つの新規プロダクトを発表しました。
今回は、その新規プロダクトについて、新規事業室に所属するデータサイエンティストの谷口と、代表の矢本が本音で語り合いました。
小売業のDXにおける本質的な課題と、10Xが描く未来の姿とは。現場での実体験を交えながら、データ活用の新たな可能性を探ります。
本記事は、2025年7月27日に公開した、Zero Topic(ゼロトピ)の「#328 小売業のデータをアクティベーションするための基盤をつくる」のエピソードを記事化したものとなります。ぜひPodcastも併せてお聞きください。
丸紅株式会社、NPOを経て株式会社スマービーの創業から売却を経験。株式会社メルカリ子会社にて新規事業のプロダクトマネージャーを経て、10Xを創業。
サイバーエージェントにて広告プロダクトのデータ分析やアルゴリズム開発を経験したのち、機械学習の研究チームで推薦システムを担当。その後、スタートアップを経て2022年3月に入社。
小売業が抱える労働生産性の課題を解決する、5つの新プロダクト
――まずは谷口さんの現在の役割と、新規事業室での活動について教えてください。
谷口:2022年3月に入社して、ここ1年ほどは新規事業室でこれまでのネットスーパー事業とは違う領域で新しいプロダクトを作っています。現在は、新規事業群で使うデータをどう受け取り、どう活用するかという基盤づくりに特に注力していますね。
矢本:経緯を補足すると、1年半ほど前に、僕が一人で新規事業を模索していた時期がありました。その時の関心領域がデータセキュリティで、10Xのデータ構造やパイプラインの詳細をキャッチアップしたくて、「教えてほしい」と声をかけたのが谷口さんでした。
そこからは、小売の現場にも何度も一緒に足を運びましたね。二人三脚で進めて、新規プロダクトの開発も一緒に進めている、という経緯です。
――5月に発表された、今回の新規プロダクトについて教えてください。
矢本:新規プロダクトを具体的に紹介する前に、なぜその事業が必要だったかをお話しさせてください。
10Xは2020年にネットスーパープラットフォーム「Stailer」の提供を開始し、現在全国のスーパー・ドラッグストア13社に導入されています。数百億円規模の流通総額に成長し、導入企業の流通総額は市場成長率+10.5%に対して、平均+56.7%と大きく上回る成長を実現しました。
ただ、小売業界では人手不足がかつてないレベルで深刻化しています。90%以上のスーパー事業者が「人手不足により事業継続に大きな影響がある」と回答している状況です。つまり、ネットスーパーのような一部業務のデジタル化だけでは、特にこれ以上の労働生産性向上は難しいのが明らかでした。
そこで5月に発表したのが、2025年中に提供予定の5つのプロダクト群です。小売業が抱える労働生産性の課題を、より直接的に解決するためのソリューションです。
Stailer AI発注は売上・天候・販促情報をもとにAIが最適な発注を提案し、属人化を解消します。Stailer AIプライシングは販売実績から粗利目標に応じた最適価格を算出することができます。Stailer MDは小売・卸・メーカー間で商品データの整備と活用を標準化する基盤です。Stailer OMNIは既存の店舗IDやポイントシステムと、ネットスーパーのシステムを統合するOMOアプリです。そして、それら全ての基盤となるのが、Stailerデータストアです。
小売業界のデータ活用がうまく進まない複雑な事情
――なぜデータがそこまで重要なのでしょうか。
矢本:小売業のDXを実現するには、データのアクティベーションが不可欠だからです。今後AIを活用していこうと思った時にも、ドメインデータをちゃんと使える形で持っていないと、本質的な課題解決にはたどり着けません。
実際にPoCや検証を重ねる中で、小売業のデータには想像以上に深刻な課題がありました。まず第一に、データが取り出せない、あるいは綺麗に整っていません。小売業が使う基幹システムとPOSシステムに重要なデータが眠っているのに、取り出すのに膨大なコストがかかります。第二に、欲しいデータが活用を見据えた形で入っていません。そして第三に、これらの問題によってデータ活用自体が進んでいない現状がありました。
こうしたデータのアクティベーションこそが、小売業DXの本質的課題だと僕は見ていますが、谷口さんの意見も聞いてみたいです。
谷口:矢本さんの指摘に同意です。技術的な観点から補足すると、まず「取り回し」の課題が深刻ですね。
基幹システムのデータは、あくまで基幹システムのためだけのデータでしかありません。例えばネットスーパーを始める際も、そのためのデータを基幹システムから作り直す必要があります。毎回この作業に時間もコストもかかっています。
さらに、新規プロダクトを展開していく中で、プロダクトごとに必要なデータが異なるということも明らかになってきました。AI発注にはこういうPOSデータ、プライシングには別の形式のPOSデータといった具合に、毎回個別にデータ連携の仕組みを作る必要があるのです。これでは、連携コストが際限なく膨らんでしまいます。
矢本:実際、我々が最初にぶつかったのも、基幹システムの仕様変更に対応するデータコネクター開発でしたよね。
谷口:そうです。取り回すだけでも時間がかかるというのには、かなり頭を悩ませましたね。
ただ、ネットスーパーのための分析基盤を作ってきた知見が、今の新規事業のデータストアにも活きています。積み上げてきたものを次の事業に使えているな、という感覚はありますね。
――先ほど「欲しいデータが活用を見据えた形で入っていない」という課題が上がっていました。これはデータの品質にも関わる問題だと思いますが、具体的にはどのような課題があったのでしょうか。
谷口:品質の問題は、取り回し以上に深刻だったかもしれません。というのも、データは普通のソフトウェアと根本的に違うんです。スキーマを定義したらその通りであればいい、というわけにはいきません。なぜならオペレーションの中で人が関わる以上、必ずエラーが混入するからです。
例えば、文字列は入っているけど、そもそも存在しない文字列になっていたり、必要なオペレーションが抜けてデータが欠損していたり。データは流動的な性質を持つため、品質の担保が本当に難しいです。
矢本:しかもこれらの問題って、ビジネスの上流工程では見過ごされやすいですよね。実際にデータを受け取って使うタイミングで、やっと「あれ、このデータおかしいぞ」と気づくんです。これがかなり多い印象です。
谷口:そもそも小売業界でデータを本格活用している企業は、僕の印象だとまだ少ないです。自分たちのデータを普段見る機会がないから、実際にデータを使う場面になってから露呈する問題がたくさんあります。
使いやすいデータがない、データを使えるツールがない、データを扱うスキルがないなど、データ活用が進まない理由は複合的です。これらが絡み合ってデータ活用を阻んでいるから、一筋縄ではいきません。
小売企業のデータを一元管理する基盤「データストア」を構築
――こうした複雑な課題を、どう解決しようと考えたのでしょうか。
矢本:小売業のドメインデータを扱える環境を作ることが、まずは必要不可欠だと考えました。
取り回しの問題、データの品質の問題、そもそもデータ活用が進んでいない問題です。これらの課題を解決しない限り、どんなに優れたDXソリューションを作っても機能しません。現状のままだと、小売業側は複数のデジタルツールを導入したくても、どこかでつまずいてしまいます。我々10X側も、事業の対象市場を広げて様々な課題を解決したくても、データ基盤がなければ実現できませんから。
そこに向けてどう進めてきたのか、谷口さんから話してもらえますか。
谷口:はい。まず複数のプロダクトに対して、いろんなデータが必要になるというところがポイントでした。それを解決するために「データストア」という構想を立てました。データストアは、簡単に言えば小売企業のデータを一元管理する基盤です。
データストアでは、小売企業から受け取った全てのデータを一箇所に集約します。これがSSOT(Single Source of Truth:単一の情報源)という考え方です。そして、各プロダクトには必要なデータだけを提供します。例えば、AI発注には発注に必要なデータだけ、プライシングには価格設定に必要なデータだけを送ります。そうすることで、一つのデータハブから、複数のプロダクトを効率的に動かせるようになります。
副次的なメリットとして、データが一箇所に集まるので、今まではプロダクトごとに行っていた品質チェックを一箇所でできるようになります。
――品質チェックを一箇所でできるのは効率的ですが、データの品質はどう保証するのでしょうか。
矢本:谷口さんが「データコントラクト」という考え方を提案してくれました。
谷口:データには、質の悪いデータを入れれば、質の悪い結果しか出ない「ガベージイン・ガベージアウト」という本質的な課題があります。この問題を解決するのが、データコントラクトです。
具体的には、データを作る人が品質を保証する仕組みです。Stailerの中に入ってきたデータは、データの生産者から提示されたコントラクト(契約)で品質を保証します。これによってデータの循環全体で品質を担保できるようになりました。
さらに、入ってくるデータだけではなく、データ生成そのもの改善も行おうと考えています。Stailer MDは、まさにその構想からできたサービスなんです。一次データの段階から品質を保つ仕組みを作ることで、根本的な解決を図っています。
――データの品質を保つために、他にも重要なポイントはありますか。
谷口:実は、UI/UXがデータ品質を大きく左右するんです。人のオペレーションがデータを作る以上、最後は必ず人の作業が入ります。どういうデータを取るかも大事ですが、それを入力する人に、「良いデータが入力できる体験」を提供できるかが重要なんです。
矢本:入力作業が面倒だったり、実際の業務フローと合っていなかったりすると、そもそもデータを入力してもらえません。既存の多くの基幹システムが、まさにこの問題を抱えているんですよね。使いづらいから適当に入力される、あるいは入力自体をスキップされてしまいます。
UI/UXの改善がデータ品質の改善につながるという気づきは、今後のプロダクト開発にも活かしていきたいですね。
AIプライシングは、市場を広げるためのエントリープロダクトになっていく
――新規プロダクトの中で、特に反響を感じているものはありますか。
矢本:AIプライシングですね。構想レベルのスライド数枚だけで、何社も受注が決まったくらい、手応えは想像以上です。
なぜこれほど響いたのか。それは、小売業が今まさに直面している利益確保の課題に、ピンポイントで応えられたからだと思っています。現在、小売業は二重の圧力を受けています。インフレで仕入れ価格は上昇し、同時に人件費も高騰しています。しかし、競争が激しくて簡単に販売価格を上げられません。結果として利益が圧迫され、事業継続性が揺らいでいるのです。
この状況で必要なのは、「どの商品をいくらで売れば利益を最大化できるか」を的確に判断することです。AIプライシングは、利益を最大化する価格を、自動算出するサービスです。今の小売業界が抱える課題を、直接解決できるプロダクトを提供できたことが、反響の高さにつながっていると考えています。
谷口:ネットスーパー事業と今回のプロダクトには、決定的な違いがあります。ネットスーパーは、弊社のStailerネットスーパーを提案しても、まずネットスーパーを開店するかを検討するところから始まることが多いです。だから市場が限定的です。一方、プライシングや発注は違います。これらは全ての小売企業が毎日のように行っている業務です。つまり、AIプライシングは、日本中の全ての小売企業が顧客になる可能性を秘めているんです。
まずプライシングや発注といった必須業務のプロダクトで、10Xとの取引を始めてもらいます。そこから信頼関係を築いて、他のプロダクトも検討してもらえるようになるかもしれません。複数のプロダクトを導入してもらえれば、データストアの「一つのデータハブで複数プロダクトを動かせる」という真価が発揮されます。
そういった意味で、AIプライシングは市場を広げるためのエントリープロダクトとして、これ以上ないポジショニングを築いていけると考えています。
――AIプライシングがエントリープロダクトとして機能するということは、データストアの価値も段階的に発揮されるということでしょうか。
谷口:データストアの真価は、まさに複数プロダクトの連携にあります。今後、AIプライシングから入った企業が、次にAI発注も導入したいとなった時にデータストアがあれば、追加のデータ連携は最小限で済みます。
矢本:1つのプロダクトだけなら、従来通り個別のデータ連携でも対応できます。でも2つ、3つとプロダクトが増えるごとに、データ連携も複雑になっていきます。
データストアがあれば、この問題が解消されるんです。一度データストアにデータを入れれば、10Xのプロダクトならそれ以降はスムーズに導入できます。これが「一つのデータハブで複数プロダクトを動かす」という構想の本質です。
実際、去年から複数プロダクトを同時導入する事例が出始めているんですよ。思い描いた構想が現実になりつつある手応えを感じています。
企業規模に関係なく、小売業界全体で「本当の意味での効率化」を目指していく
――谷口さんは新規事業の開発のため、小売の現場にも深く入り込んだと聞きました。その理由は?
谷口:僕が意識しているのは、データそのものより「データの生成過程」を理解することです。データベースに入っているデータを見て分析するだけでは、なぜそのデータがそういう形で入っているのか、本当の意味では理解できないと思っています。
データがどの業務で、誰が、どんなタイミングで入力したものなのか。この生成過程を知らなければ、データの本質は理解できないんです。文字列が何桁かという話は、システムレイヤーの都合でしかありません。データは本来、システムに依存しないものですから。
矢本:谷口さんの現場への入り方は、本当に徹底していますよね。商談についていくだけじゃなく、お店で早朝作業してるところまで入っていくんです。谷口さんと現場に行って、データベースの中身と現場業務が全て繋がっている状態を目の当たりにして、データエンジニアリングの知見は、事業開発に不可欠だと実感しました。
――今後の展望についてお聞かせください。
矢本:AI発注やAIプライシングは、企業規模を問わず導入できるプロダクトです。ネットスーパー事業は、エンタープライズ向けの製品でした。一方、今回のDX系製品は地方の中小スーパーでも導入可能です。まずは10Xのソリューションを使っていただける企業を増やし、その後でプロダクトを磨き上げていくことが、次の1、2年の目標です。
谷口:技術面では、AIを活用した本当の業務効率化を実現したいと考えています。例えば発注時間を短縮しても、それだけではPLは変わりません。人員削減まで実現して初めて、本当の効率化と言えます。そして浮いた価値をエンドユーザーに還元する。そこまでやり切りたいです。
また、小売業界はまだ「勘と経験と度胸」に頼る部分が多いんです。それ自体は悪くありませんが、データを使えばもっと効率化できるはずです。縦割りの業務を改善し、一人一人がより広い範囲を見られるようにするためには、データでコミュニケーションすることが重要です。小売企業がこれを実現できるよう、支援していきたいですね。
――最後に、どんな仲間を求めているか教えてください。
矢本:今日は、小売業のデータ基盤構築から新規プロダクト開発まで、全体像をご紹介できたかと思います。ただ、これらを実現し伸ばしていくためには、まだまだ足りないものがあります。
谷口:新規事業の拡大で、プロダクトもお客様も増えています。それに伴い、データ処理やシステムを支える人材が必要です。現在はソフトウェアエンジニアやSREとデータ基盤チームが密に連携していますが、今後の展望を実現するには人が足りません。
矢本:僕もよく面接に参加するのですが、特にデータエンジニアの方とお話する機会がないように感じていて……。もっと話したいなと思っています!
谷口:矢本さんにその機会を届けられるように、僕も頑張ります(笑)。データエンジニアの他にも、ソフトウェアエンジニア、SRE、プロダクトマネージャーを特に募集しています。小売業のDXという社会的意義のある仕事に興味がある方は、ぜひご連絡お待ちしています!
10Xでは一緒に働くメンバーを募集中です!
10Xでは未来をより良くする事業・組織のために、仲間を募集しています。
詳細はこちらをご覧ください。



